皆さんは応用情報技術者試験の午前問題をどのように学習していますでしょうか?
私は令和6年秋の試験を受けて、午前問題の学習方法が間違っていたことに気付きました。
過去問だけをダラダラ解いていたため、全然実力がついておらず、午後試験は散々な結果だったのです。
今回は、私の経験をもとに、午前問題の学習方法を紹介していきます。
- 応用情報技術者試験の学習をしている方
- これから受験を考えている方
- 学習方法で悩んでいる方
【応用情報午前書籍】
私が午前対策でおすすめするのは「キタミ式」です。
イラストが多いので様々な用語を関連付けて覚えることができます。
図などで関連付ける方が記憶に定着しやすいと言われています。
ぜひ手にとって勉強してみてください。
参考書を通読する
資格勉強のお供といえば参考書ではないでしょうか。
私も参考書には非常にお世話になっているうちの一人です。
ですが、参考書は飽きるという方も中にはいらっしゃるでしょう。
私もその中の一人です。
なので私は、参考書を読むのは一度きりにしてます。
あとは、過去問を解いていってわからないところを辞書代わりに使うという方法をとっています。
参考書は索引としては非常に優秀で、大体の参考書の最後に索引ページがあります。
 Hachi
Hachi流し読みでも結構です。ある程度の内容把握が目的になります。
参考書選びのコツ
応用情報の対策用のテキストは多くの数があります。
様々な出版社から出ていますし、現代では紙なのか電子なのかも悩みどころ。
私は紙をおすすめします。
紙の本なら寝る前に読むことが可能です。
電子だとブルーライトを浴びてしまうため、睡眠の質が落ちてしまいます。
次にどのような書籍を選ぶか。
他人と自分は違います。
書店などで実際に中身を見て、自分が分かりやすいと思えるものを選ぶべきです。
レビューの評価が良くても、自分に合わなければ本末転倒。
自分の感覚を信じて参考書を選びましょう!
参考書から重要語句を抜き出す
あと私が行っているのが、参考書から重要語句を抜き出してノートに写すことをしています。
このような感じです。


字が汚くてすみません。。。
一番左が用語、真ん中が用語の意味、一番右が用語が記載の参考書のページ番号です。
左側を隠せば用語をアウトプットできますし、真ん中を隠せば意味をアウトプットできます。
重要語句はどのように抜き出すかというと、参考書に赤字で書いてあるものを抜き出します。
参考書を作っている人はその資格のプロと言えるでしょうから、赤字部分イコール重要だと解釈して問題ないでしょう。
インプットと同時にアウトプットも行う
参考書を読むだけだと、いつまでも内容を理解できないので、アウトプットも同時に行うことをおすすめします。
応用情報だけでなく、勉強全般に言えることですが、勉強はインプットよりもアウトプットの比重を重めに設定する方がよいです。
試験はアウトプットをする場だと思えば、アウトプットの重要性が分かるのではないでしょうか。
では一体どれくらいの割合なのか。
私がおすすめするのは、下記の割合です。
- インプット2~3割
- アウトプット7~8割
かなりアウトプットに重きを置いていますが、試験でもアウトプットが試されるので、これくらいでもよいはずです。
またインプットだけをひたすら行うと飽きる可能性が高いでしょう。
勉強は基本的に楽しくないと続かない、特に大人になればなおさらで、勉強を楽しむことが最も重要だと言えます。
次で紹介する過去問と並行して行うこともおすすめです。
過去問を解く
資格試験はやはり、過去問を解くのが一番の学習方法だと思います。
特に応用情報技術者試験の午前問題は4割から5割程度が過去問からの流用です。
過去問を解くのは必須といえるでしょう。
過去問は下記サイトで学習できます。
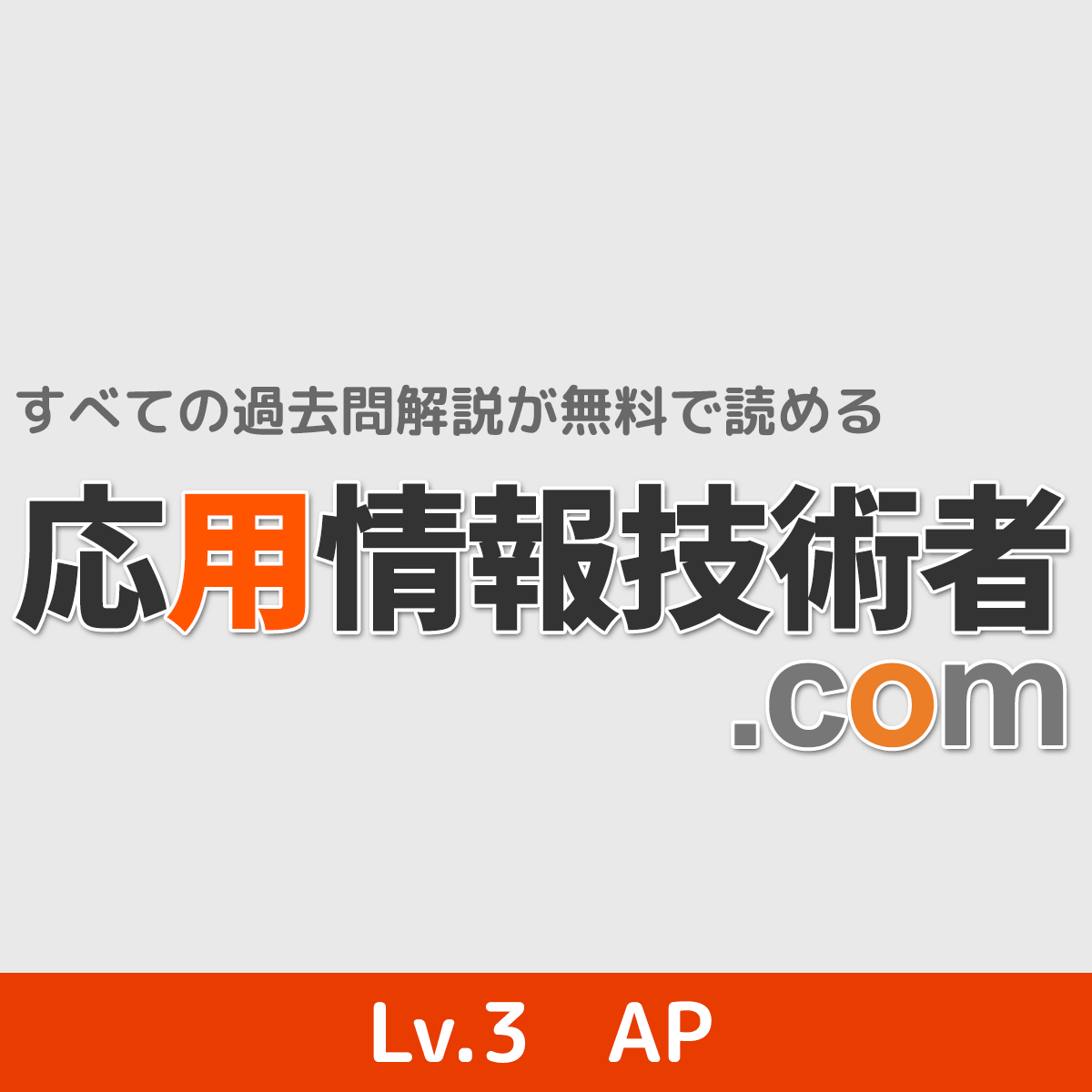
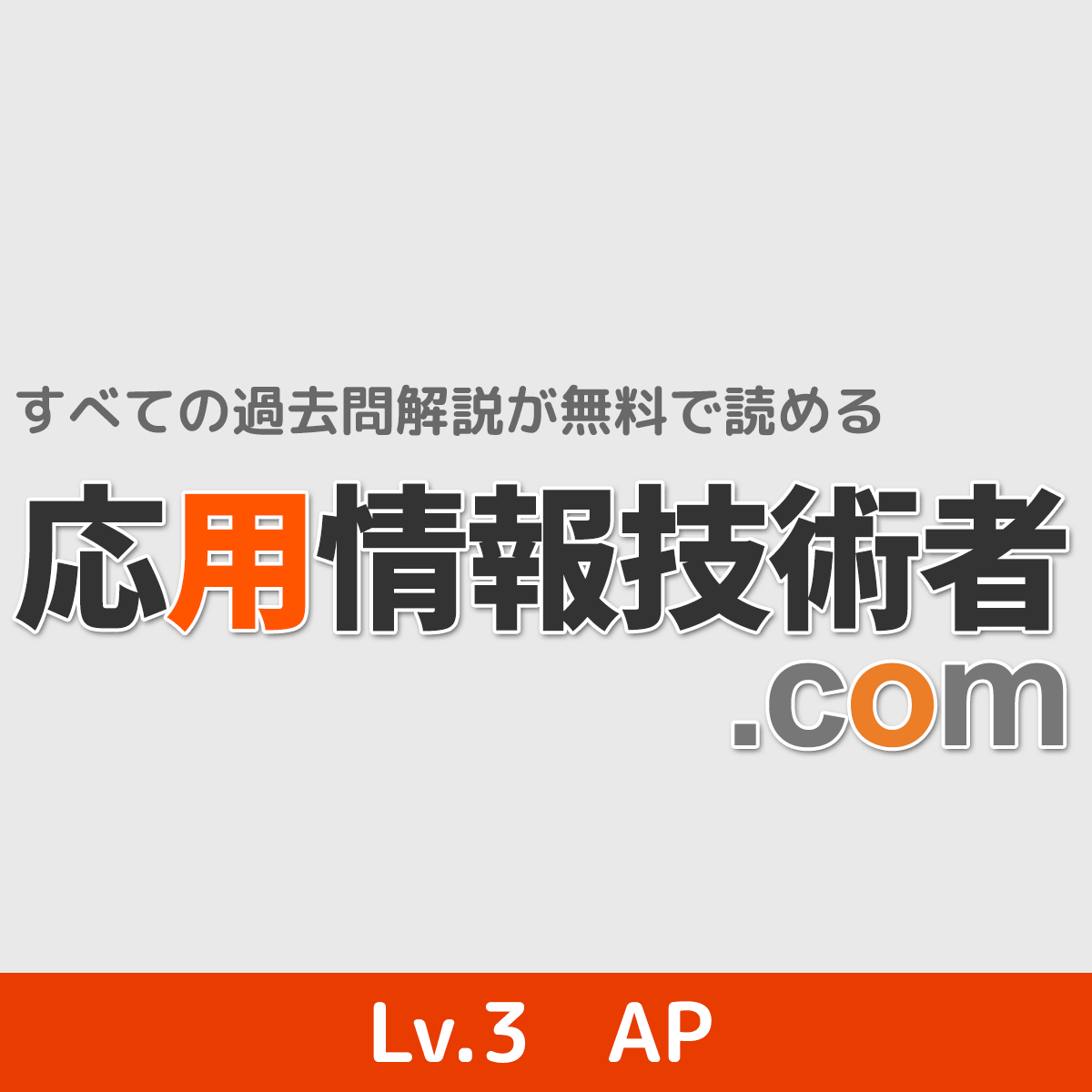
直近2回分からは同じ問題が出題されないという統計が出ていますので、過去問を学習する際は直近2回より前の年度の学習をするとよいでしょう。
過去問道場のいいところが、問題の解説までされていることです。
間違えた問題は、解説を確認して知識として落とし込みましょう。
過去問から関連ワードも学習する
午前問題はア~エの4択で、正解は一つになります。
ですが、正解の用語だけを学習するのはよくない勉強法になります。
不正解の残り3つの用語が試験問題として出題される可能性があるからです。
さらに関連用語は午後問題でも問われることがあり、勉強しておいて損はないと思います。
それなりに学習コストがかかってしまうため、どこまで学習するかの線引きも大事になるでしょう。
応用情報はとにかく範囲が広いのですべての用語を覚えることは不可能です。
一つの案として、午後問題で選択する用語は覚えるといった作戦があります。
自分が選択する分野の用語は勉強しておいた方が良いので、午後問題で覚える覚えないの線引きをしても良いと思います。
午後問題で出題された用語を学習する
例えば下記は令和2年の午後試験で問われた問題です。


答えは「デジタルフォレンジック」です。
デジタルフォレンジックは午前試験でも出題される問題です。
下記は午前試験のデジタルフォレンジックに関する問題です。
つまり、午前試験と午後試験は密な関係だということ。
どちらかを疎かにしてしまうと、合格できないのが応用情報技術者試験です。
午後問題の過去問で問われた用語は、午前試験でも出題されるという認識でいましょう。
また逆もしかりで、午前試験に出題される用語は午後試験でも出題されます。
ですので、応用情報技術者試験の基礎知識はすべて午前試験に詰まっていると言っても過言ではありません。



午前試験対策がいかに重要かが分かりますね!
間違えた問題の復習を行う
義務教育で「復習が大事!」と習ったかと思います。
なぜ復習が大事なのかと言いますと、人間の記憶力はそこまでよくできていないからです。
よくできていない、というと語弊があるかもしれませんが、勉強したことを復習しないと次の日にはほとんど忘れているということをお伝えしたいのです。
これは資格試験にも同じことがいえます。
例えば、親の名前や自分の年齢は忘れることがないですよね?
これは、何度も思い出したり口に出したりしているから記憶に定着しているのです。
勉強も同じで、重要な事柄は何度も繰り返し思い出す。
これをすることで記憶に定着して、試験でも思い出すことができるのです。
特に、間違えた問題については必ず復習をしましょう。
復習方法は下記記事で紹介しています。
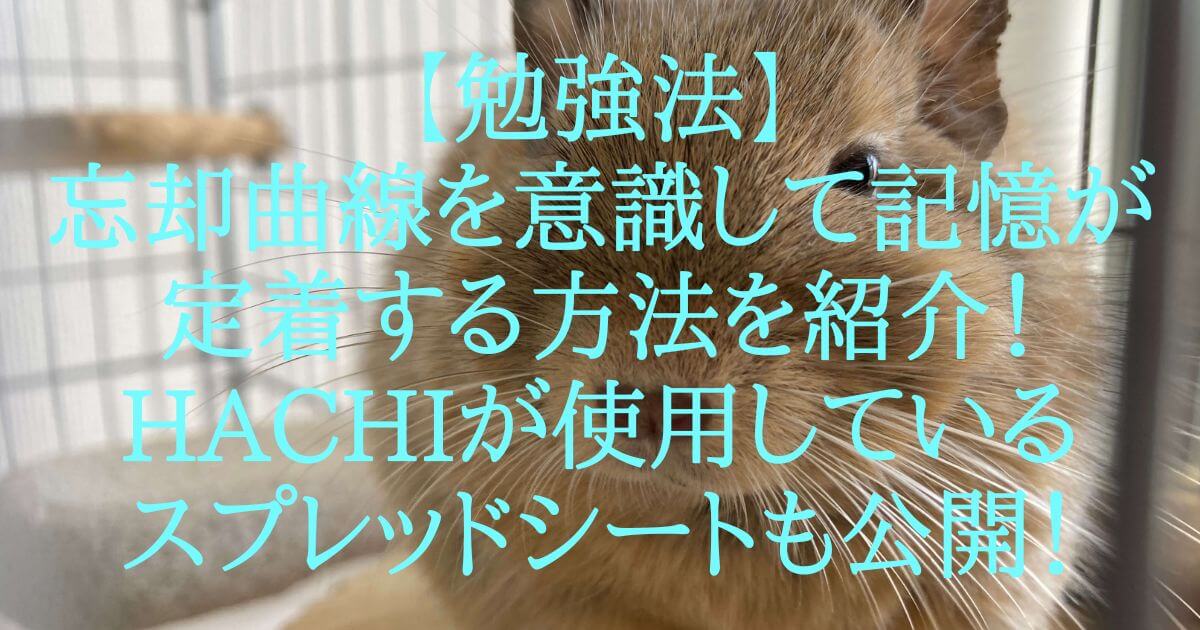
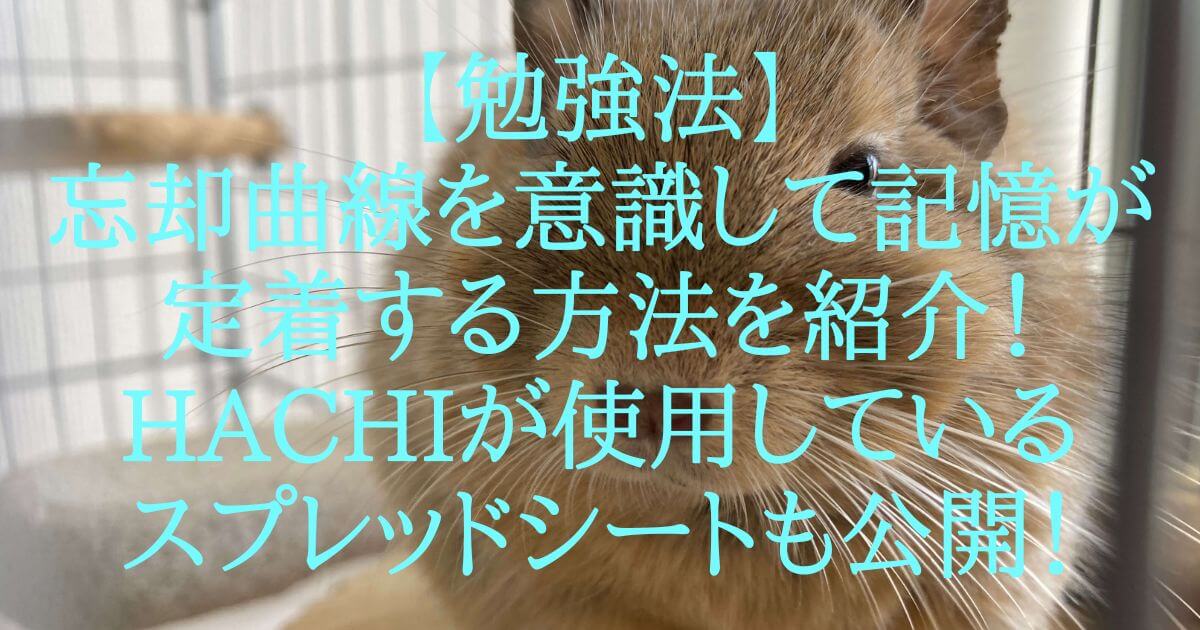
復習を行う期間を意識しよう
午前問題を特に意識することなく復習することはあまりおすすめしません。
なぜなら、人間の記憶は忘れる期間が大抵決まっているからです。
「エビングハウスの忘却曲線」というものに沿って復習すると、記憶に定着すると言われています。
詳しくは下記記事で解説しています。
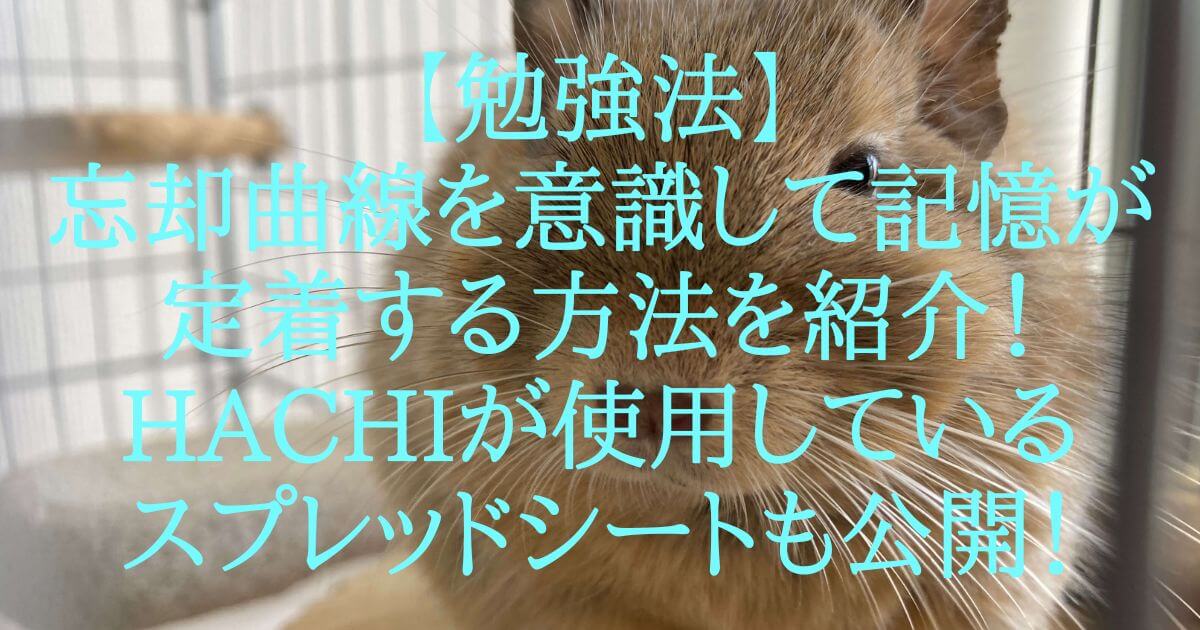
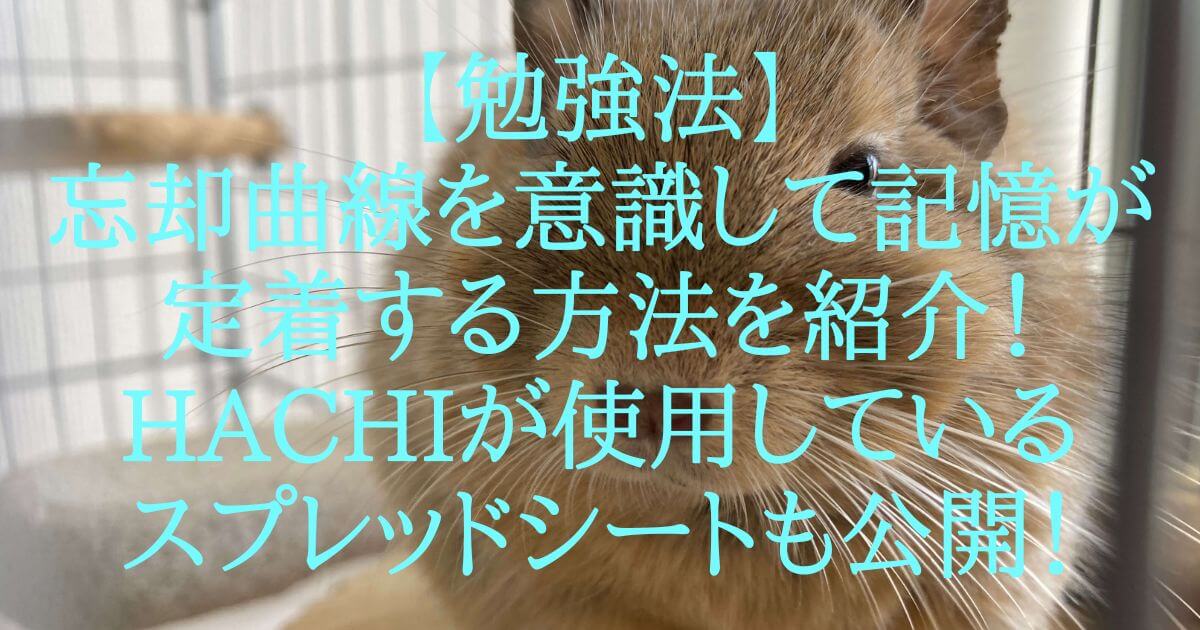
これに沿って復習をすることにより、記憶に定着して午前試験も難なく攻略することができると思います。
午前試験は過去問から4~5割程度出題されます。
過去問を覚えるだけで、一気に合格圏内に入ることができます。
ぜひ、エビングハウスの忘却曲線を利用してみてください。
まとめ
今回は応用情報技術者試験の午前試験の学習方法について解説しました。
正直、午前試験よりも午後試験の方が難しいのですが、基本的な午前試験の知識がないと午後はまず合格点に達することができないでしょう。
まずは用語の理解とインプットが大事です!
そして、ある程度知識が身についてきたら、午後試験の対策に入ることを推奨します。
知識という武器を身に着けて、試験という戦場でよい結果を残しましょう。
私自身、この方法で午前試験突破できています!
検討を祈ります!
関連記事
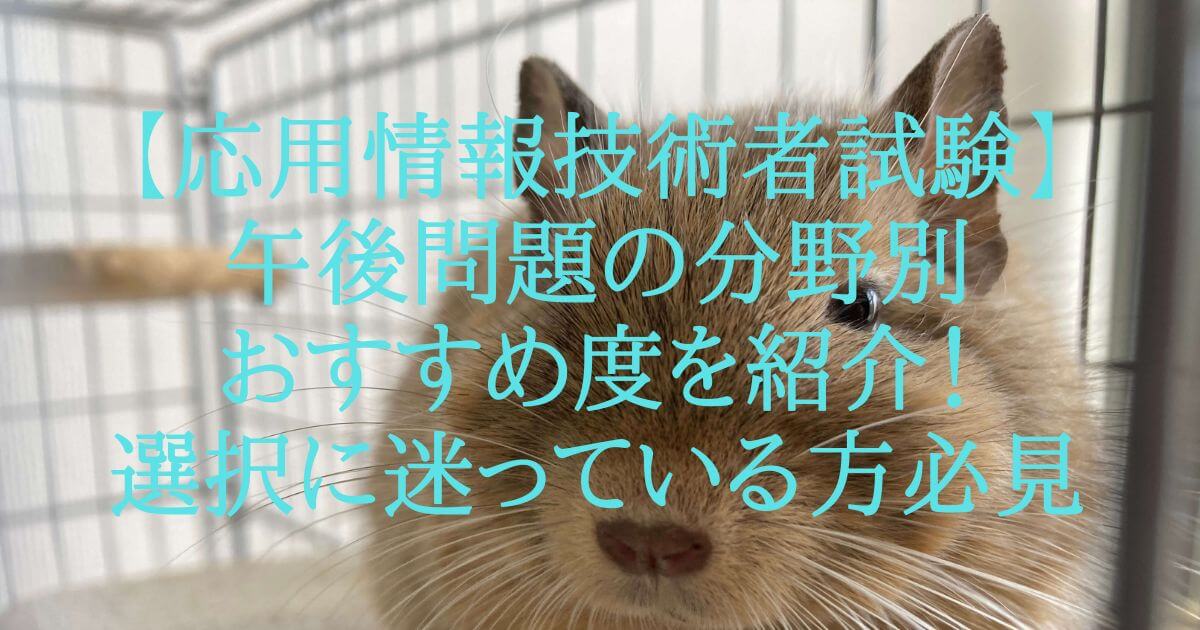
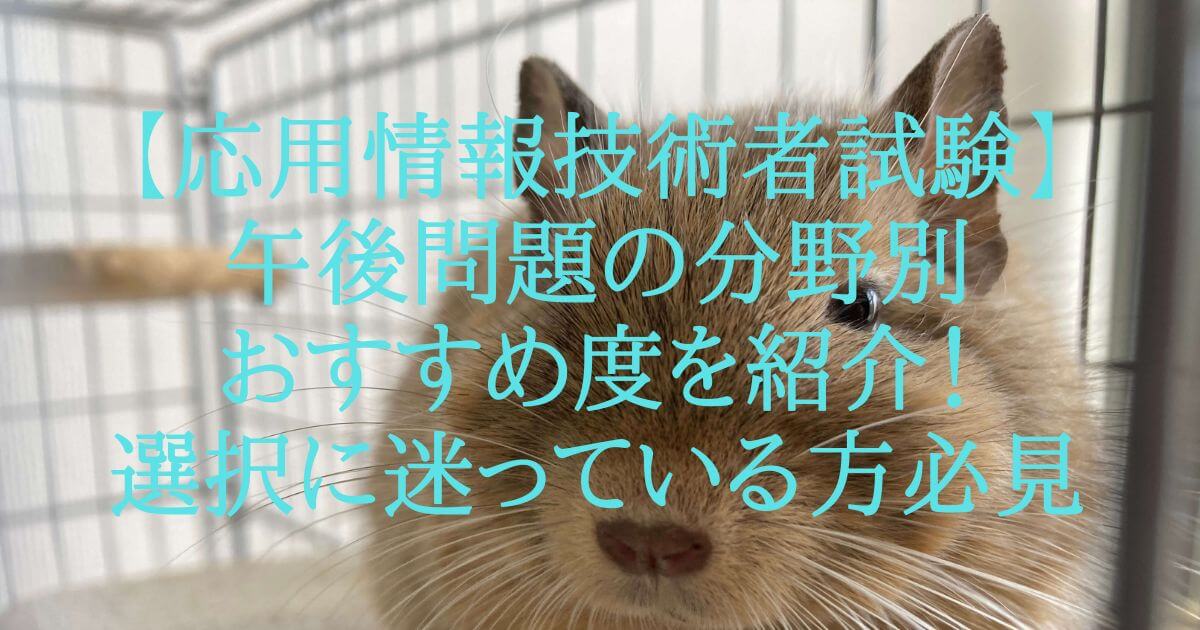
おすすめ書籍
【応用情報午前書籍】
私が午前対策でおすすめするのは「キタミ式」です。
イラストが多いので様々な用語を関連付けて覚えることができます。
図などで関連付ける方が記憶に定着しやすいと言われています。
ぜひ手にとって勉強してみてください。
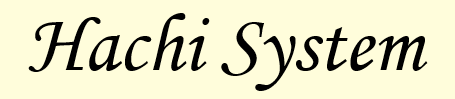
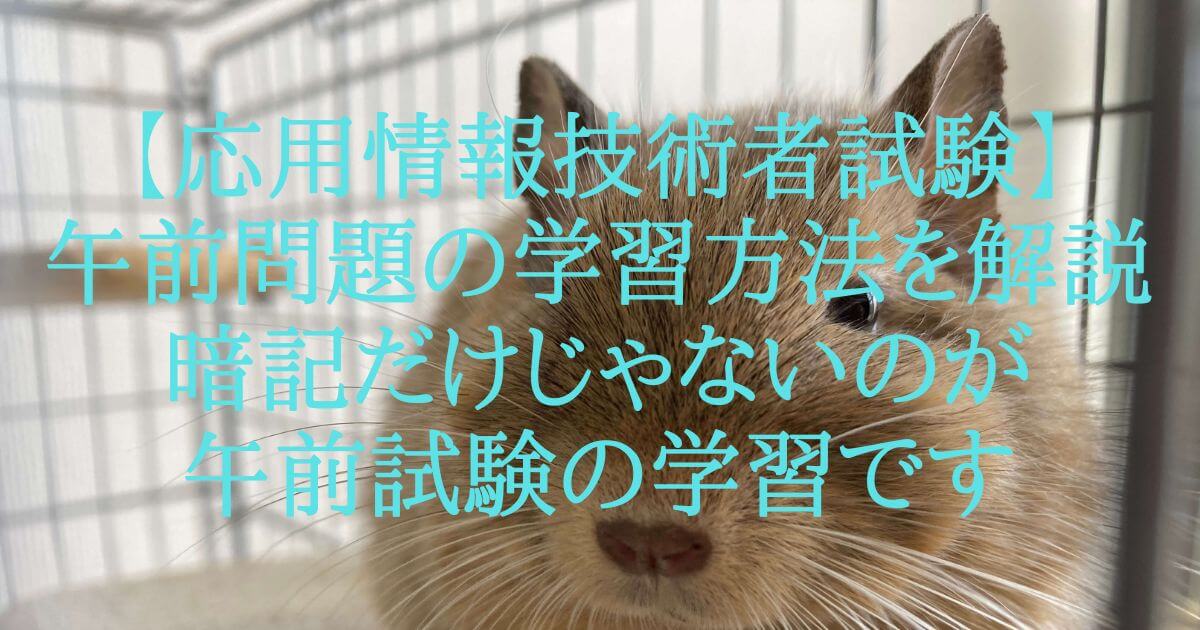
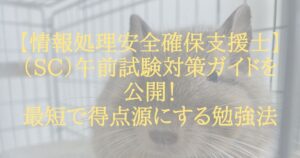
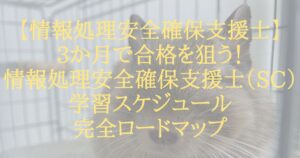
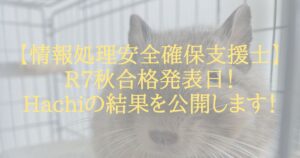
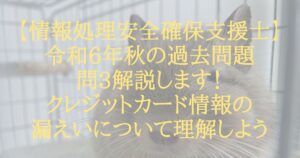
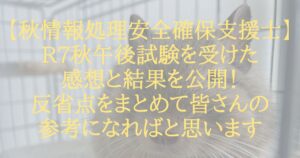
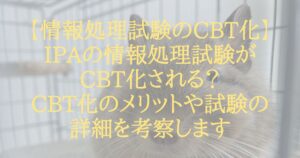
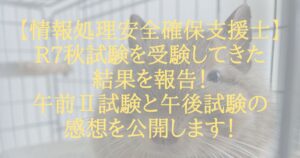
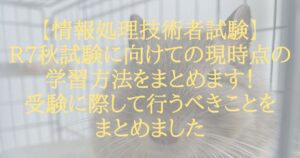
コメント